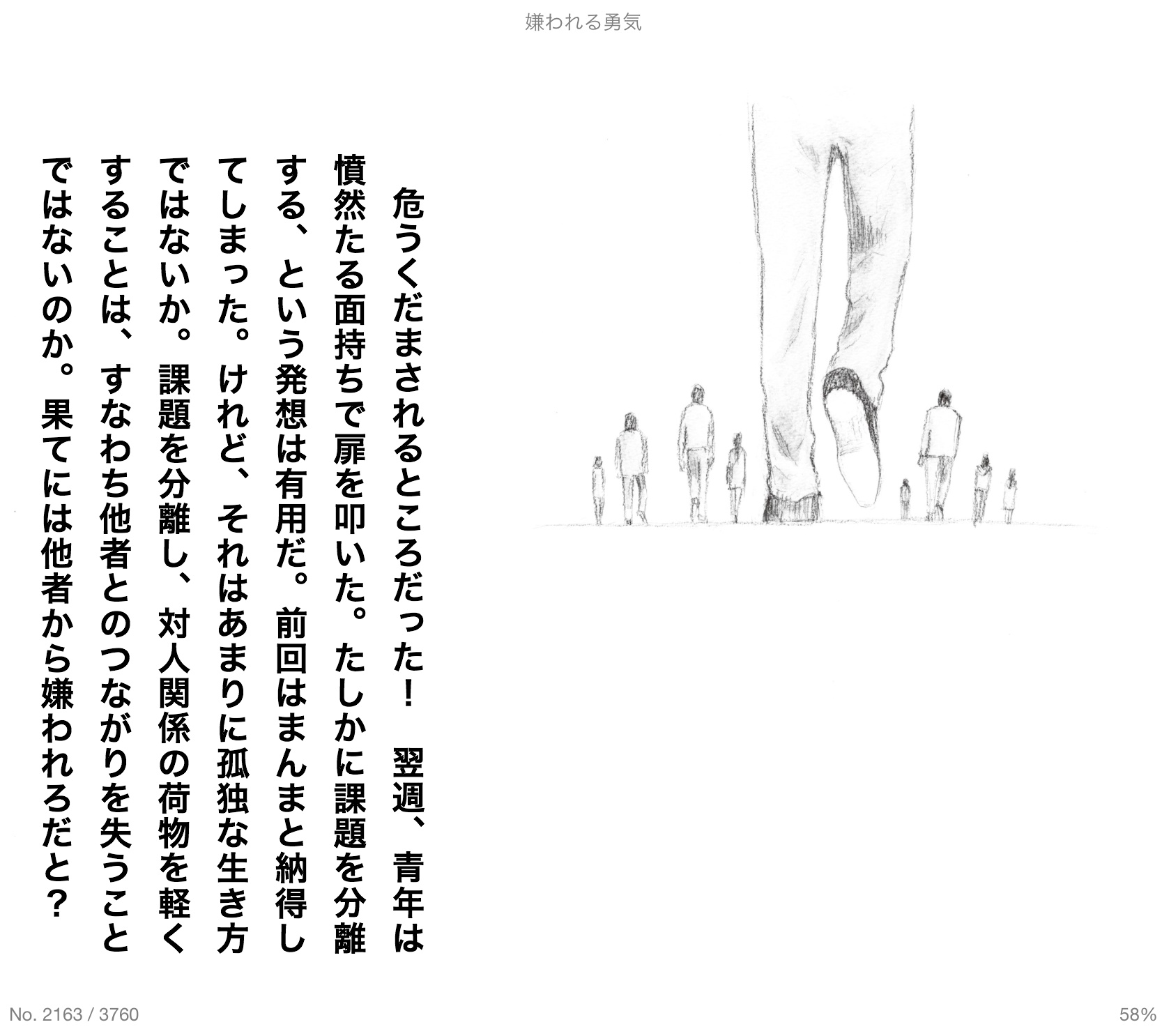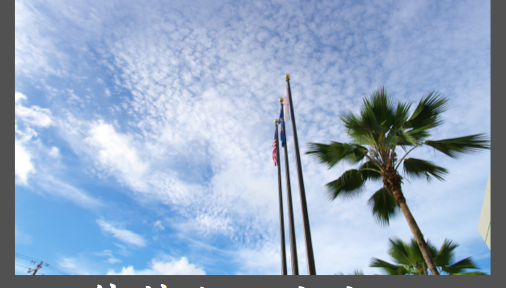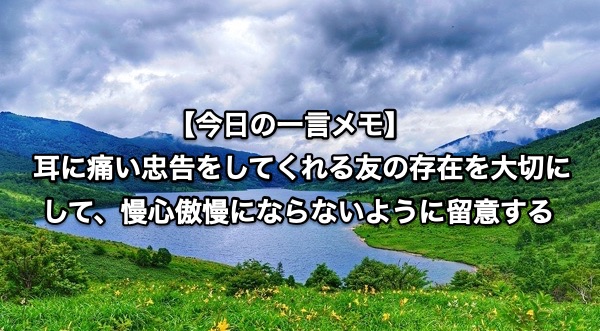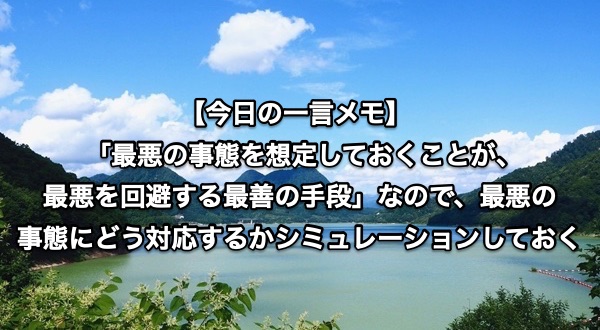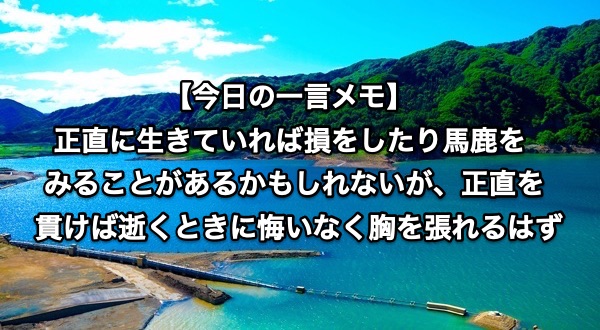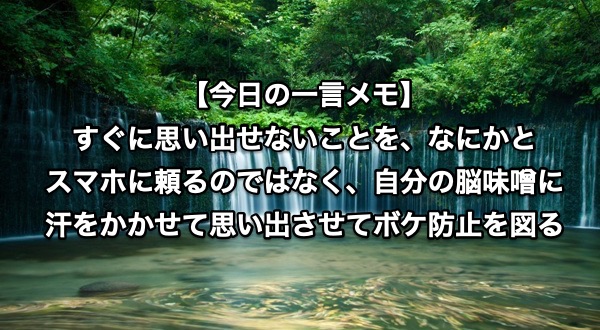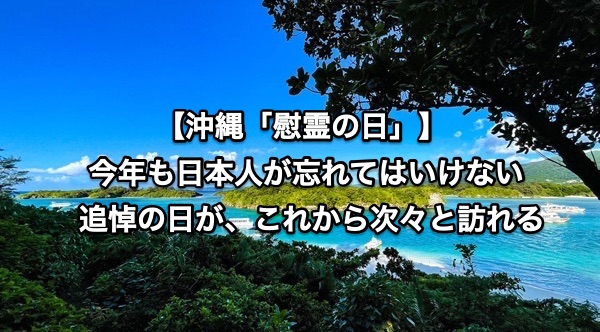前回まで3回にわたり、Kidle電子書籍の「嫌われる勇気」を読んで感じたことを書いてきました。
「第一夜 トラウマを否定せよ」
「第二夜 すべての悩みは対人関係」
「第三夜 他者の課題を切り捨てる」
今回は、「第四夜 世界の中心はどこにあるか」を読んで感じたことを書いてみます。
「第三夜 他者の課題を切り捨てる」まとめ
前回の第三夜では、いよいよ本書のタイトルである「嫌われる勇気」の核心が示されました。曰く「自由を行使するためにはコストが伴う、そして対人関係における自由のコストとは他者から嫌われることなのだ」と。
そして、「嫌われる」という言葉については「他者からどう思われようと構わない」という意味に拡大解釈してみました。そして、その心持ちに至るには大きな勇気が必要であることも、富田の経験から実感できるものでした。
また、自分の課題と他者の課題を明確に分離し、他者の課題には介入しないこと、とする考え方は理解できても、実行することはなかなか難しいように思いました。良かれと思って他者にアプローチすることが、「援助」の範囲なのか「介入」にあたるのか判断しかねることがありそうだったからです。その点については、第四夜で明らかになっていきます。
第三夜から一週間後、青年が憤然とした様子で哲人の書斎に現れました。
第四夜 世界の中心はどこにあるか
それでは第四夜からキーワードを引用します。
個人心理学と全体論
青年は課題の分離は無理があるという。それは結局「わたしはわたし、あなたはあなた」と境界線を引いていくような発想ではではないか。そんな生のあり方は本当に正しいといえるのか。
アドラー心理学は「個人心理学」とも言われるが、これは個人主義というわけではない。英語でいう個人(individual)という言葉は、語源的に「分割できない」という意味を持つ。
心と身体、理性と感情、意識と無意識についても不可分であり一体であるとみなす。よって、感情のみで人が動くことはなく、全体として動いている。
このように、人間をこれ以上分割できない存在だと捉え、「全体としてのわたし」を考えることを「全体論」と呼ぶ。
課題の分離は、他者を遠ざけるための発想ではなく、複雑に絡み合った対人関係の糸を解きほぐしていくための発想なのだ。
対人関係は、課題を分離したところで終わるものではない。むしろ課題を分離することは、対人関係の出発点である。
対人関係のゴールは「共同体感覚」
これがアドラー心理学の鍵概念であり、その評価についてもっとも議論が分かれるところ。
他者を仲間だと見なし、そこに「自分の居場所がある」と感じられることを、共同体感覚という。
アドラーは共同体について、家庭や学校、職場、地域社会だけでなく、過去から未来、そして宇宙全体までも含んだ、文字通りの「すべて」が共同体なのだと提唱している。
青年はそんな広い概念についていけない。アドラー自身も、自らの語る共同体について「到達できない理想」だと認めているくらいだ。
しかし、ここを理解しないと、アドラー心理学を理解したことにならないと哲人は言う。そして、共同体感覚とは、幸福なる対人関係のあり方を考える、もっとも重要な指標なのだ、と説く。
社会の最小単位は「わたしとあなた」であり、ふたりの人間がいたら、そこに社会が生まれ、共同体が生まれる。まずは、ここを起点にして、自己への執着 (self interest) を、他者への関心 (social interest) に切り替えていくのだ。
なぜ「わたし」にしか関心がないのか
「自己への執着」を「自己中心的」と言い換えてみる。暴君や集団の和を乱すような人物といった一般的なイメージに加えて、「課題の分離」ができておらず、承認欲求にとらわれている人もまた、きわめて自己中心的なのだ。
承認欲求にとらわれている人は、他者を見ているようでいて、実際には自分のことしか見ていない。他者への関心を失い、「わたし」にしか関心がない、すなわち自己中心的である。
だからこそ「自己への執着」を「他者への関心」に切り替えなければならない。
あなたは世界の中心ではない
自分の人生における主人公は「わたし」であるが、「わたし」は世界の中心に君臨しているのではない。「わたし」は人生の主人公でありながら、あくまでも共同体の一員であり、全体の一部なのだ。
世界地図は自国を中心に描くので、他の国の人から見れば、自分が不当に端へと追いやられたような、世界を恣意的に切り取られたかのような、名状しがたい違和感を抱くだろう。
しかし、地球儀で世界を捉えた時は、すべての場所を中心にして見ることができる。そして、すべての場所が中心ではない。「自分が世界の中心にいるわけではない」ことも同じ。あくまでも共同体の一部であって、中心ではない。
われわれはみな「ここにいてもいいんだ」という所属感を求めている。アドラー心理学では、所属感とはただそこにいるだけで得られるものではなく、共同体に対して自らが積極的にコミットすることによって得られるのだと考える。
積極的なコミットとは、「人生のタスク」に立ち向かうこと。つまり、仕事、交友、愛という対人関係のタスクを回避することなく、自ら足を踏み出していく。
共同体の中で「この人はわたしになにを与えてくれるのか?」ではなく、「わたしはこの人になにを与えられるのか?」を考えなければならない。それが共同体へのコミットとなる。
所属感とは、生まれながらに与えられるものではなく、自らの手で獲得していくものである。
より大きな共同体の声を聞け
青年は整理する。まず、対人関係の入口には「課題の分離」があり、ゴールには「共同体感覚」がある。そして共同体感覚とは、「他者を仲間だと見なし、そこに自分の居場所があると感じられること」である、と。
しかし、「共同体」なるものが宇宙全体に広がり、過去や未来、生物から無生物まで含む、という意味を掴めない。
哲人は続ける。共同体の範囲は、さしあたって「無限大」なのだと考えればよいと。学校や会社などの小さな単位の共同体で、いじめにあったり定年退職したりして自分の居場所がなくなっても、もっと大きな共同体があることに注目して欲しい。
ひとたび世界の大きさを知ってしまえば、学校や会社という小さな世界で感じていた苦しみは「コップのなかの嵐」であったことが分かるだろう。コップの外に出てしまえば、吹き荒れていた嵐もそよ風に変わる。
大きな世界に飛び出すのは難しいかもしれない。そこで覚えておくべき行動原則がある。われわれが対人関係のなかで困難にぶつかったとき、出口が見えなくなってしまったとき、まず考えるべきは「より大きな共同体の声を聴け」という原則。
学校なら学校という共同体のコモンセンス(共通感覚)で物事を判断せず、より大きな共同体のコモンセンスに従うこと。
小さな共同体で権威をかざす人間がいたのなら、それはその共同体だけで通じるコモンセンス。理不尽な要求を突きつけられたのなら、正面から異を唱えてかまわない。もしも異を唱えることで崩れてしまう程度の関係なら、そんな関係など最初から結ぶ必要はない。
関係が崩れることだけを怖れて生きるのは、他者のために生きる、不自由な生き方。
叱ってはいけない、ほめてもいけない
青年は問う。「課題の分離」から「共同体感覚」へと進むための道筋は何か?と。
哲人は答える。どうすれば互いに協調し合って、協力し合えるような関係に繋がるのか?ここで登場するのが「横の関係」という概念。
子育ての場面、あるいは部下の育成などの場面で、一般的には「叱って育てる方法」と「ほめて育てる方法」の二つのアプローチがある。
アドラー心理学では、子育てをはじめとする他者とのコミュニケーション全般について「ほめてはいけない」という立場をとる。無論、体罰はもってのほか、叱ることも認めていない。
ほめるという行為には「能力のある人が、能力のない人に下す評価」という側面が含まれている。つまり「えらいわね」とか「よくできたわね」「すごいじゃない」とほめる母親は、無意識のうちに上下関係をつくり、子どものことを自分より低く見ている。「ほめること」の背後にある上下関係、縦の関係を象徴している。
人が他者をほめるとき、その目的は「自分よりも能力の劣る相手を操作すること」なのだ。そこには感謝も尊敬も存在しない。
われわれが他者をほめたり叱ったりするのは「アメを使うか、ムチを使うか」の違いでしかなく、背後にある目的は操作である。アドラー心理学が賞罰教育を強く否定しているのは、それが子どもを操作するためだからである。
アドラー心理学ではあらゆる「縦の関係」を否定し、すべての対人関係を「横の関係」とすることを提唱している。これがアドラー心理学の根本原理。
「同じではないけれど対等」という言葉に表れている通り、対等すなわち「横」である。例えば会社員の夫と専業主婦の妻は、働いている場所や役割が違うだけで、まさに「同じではないけれど対等」なのである。経済的な優位性など、人間的な価値にはまったく関係ない。
そもそも劣等感とは、縦の関係の中から生じてくる意識。あらゆる人に対して「同じではないけれど対等」という横の関係を築くことができれば、劣等コンプレックスが生まれる余地はなくなる。
「勇気づけ」というアプローチ
課題の分離についての説明の中で「介入」という言葉が出た。なぜ人は介入してしまうのか。その背後にあるのも、じつは縦の関係なのだ。対人関係を縦にとらえ、相手を自分より低く見ているからこそ、介入してしまう。ここでの介入は操作に他ならない。
横の関係を築くことができれば、介入もなくなる。
目の前に困っている人がいて、手を差し伸べることは「介入」だから控えたほうがいいのか?いや、見過ごすわけにはいかないので、介入にならない「援助」をする必要がある。
では、介入と援助のどこが違うのだろうか?
介入とは他人の課題に土足で踏み込み、指示すること。一方の援助とは、大前提に課題の分離があり、横の関係がある。そして他者に自信を持たせるように、自らの力で課題に立ち向かっていけるように働きかけること。この働きかけは強制ではなく、自力での解決を援助していく。
「馬を水辺に連れていくことはできるが、水を呑ませることはできない」というアプローチ。課題に立ち向かうのは本人であり、その決心をするのも本人。
ほめるのでもなく叱るのでもない、こうした横の関係に基づく援助のことをアドラー心理学では「勇気づけ」と呼ぶ。
人が課題を前に踏みとどまっているのは、その人に能力がないからではない。能力の有無ではなく、純粋に「課題に立ち向かう”勇気”がくじかれていること」が問題なのだ、と考えるのがアドラー心理学。
人は他者からほめられるほど、「自分には能力がない」という信念を形成していく。そして、ほめてもらうことが目的になってしまうと、結局は他者の価値観に合わせた生き方をえらぶことになる。
自分には価値があると思えるために
ほめるのでもなく、叱るのでもないアプローチは、まず「ありがとう」という感謝の言葉を伝える。あるいは「うれしい」と素直な喜びを伝える。「助かったよ」とお礼の言葉を伝える。これが横の関係に基づく勇気づけのアプローチ。
いちばん大切なのは、他者を「評価」しない、ということ。評価の言葉とは、縦の関係から出てくる言葉。もしも横の関係を築けているのなら、もっと素直な感謝や尊敬、喜びの言葉が出てくるはず。
ほめられるということは、他者の物差しによって「よい」と評価されたこと。もしもほめてもらうのを望むのなら、他者の物差しに合わせ、自らの自由にブレーキをかけるしかなくなる。
一方、「ありがとう」は評価ではなく、もっと純粋な感謝の言葉。人は感謝の言葉を聞いたとき、自らが他者に貢献できたことを知る。
どうすれば人は「勇気」をもつことができるのか?アドラーの見解はこうである。「人は、自分には価値があると思えたときにだけ、勇気を持てる」。
ここで問題になるのは、「いったいどうすれば、自分には価値があると思えるようになるのか?」という点。
答えはいたってシンプル。人は「わたしは共同体にとって有益なのだ」と思えたときにこそ、自らの価値を実感できる。これがアドラー心理学の答である。
共同体、つまり他者に働きかけ、「わたしは誰かの役に立っている」と思えること。他者から「よい」と評価されるのではなく、自らの主観によって「わたしは他者に貢献できている」と思えること。そこではじめて、われわれは自らの価値を実感することができる。
いままで議論してきた「共同体感覚」や「勇気づけ」の話も、すべてはここにつながる。
ここに存在しているだけで、価値がある
青年はコーヒーを飲みながら必死に頭を整理する。そしてある疑念が湧き起こってくる。誰かの役に立ててこそ、自らの価値を実感できるのであれば、生まれたばかりの赤ん坊や寝たきりになった老人や病人たちは、生きる価値すらないのではないか、と。
哲人は明確に否定する。それは、他者のことを「行為」のレベルで、すなわちその人が「なにをしたか」という次元で見ているからだ。その観点から考えると、なんの役にも立っていないように映るだろう。
そこで他者のことを「行為」のレベルではなく、「存在」のレベルで見ていく。他者が「なにをしたか」で判断せず、そこに存在すること、それ自体を喜び、感謝の言葉をかける。
もしも母親が交通事故に遭い、危篤状態にあったとしたら、意識がないので行為としてできることはないが、生きているということそれだけで、家族の心を支え、役に立っているのだ。
日常的な事例に置き換えても同じこと。ともすれば「自分にとっての理想像」を勝手にこしらえ、そこから引き算をするように評価してしまうものである。理想像としての100点から、徐々に減点する。これはまさしく「評価」の発想である。
そうではなく、ありのままの姿を誰とも比べることなく、ありのままに見て、そこにいてくれることを喜び、感謝していく。理想像から減点するのではなく、ゼロの地点から出発する。
青年は、そんなことはキリスト教の語る「隣人愛」みたいなもので、いったい誰にそんなことができるのか!と憤慨する。
同様の疑問について、アドラー本人はこう答えた。「誰かが始めなければならない。他の人が協力的でないとしても、それはあなたには関係ない。わたしの助言はこうだ。あなたが始めるべきた。他の人が協力的であるかどうかなど考えることなく。」
人は「わたし」を使い分けられない
青年は哲人に問う。「人は生きているだけで誰かの役に立っているし、生きているだけで自らの価値を実感できるのか?」と。
他の誰でもない「わたし」がここに生きているが、自分に価値があるとは到底思えないし、自信など持ちようがない、とも。
哲人はアドラー心理学から見た答を提示する。「まずは他者との間に、ひとつでもいいから横の関係を築いていくこと。そこからスタートすること。」
もしも誰かひとりとでも縦の関係を築いているとしたら、自分でも気づかないちに、あらゆる対人関係を「縦」でとらえているのである。
例え友人であっても「A君はわたしよりも上だが、B君はわたしより下だ」「A君の意見には従うが、B君には耳を貸さない」「C君との約束など、反故にしても構わない」と考えているとしたら、それは縦の関係。
逆にいえば、もしも誰かひとりとでも横の関係を築くことができたなら、ほんとうの意味で対等な関係を築くことができたなら、それはライフスタイルの大転換になる。そこを突破口にして、あらゆる対人関係が「横」になっていく。
会社組織など広い年代の中にいるのであれば、年長者を敬うことは大切であり、職責の違いは当然ある。しかし、意識の上で対等であること、そして主張すべきは堂々と主張することが大切。
青年はこの考えを理解するのに時間が必要だと考えた。そして哲人に主張を論破されたがっているのかも、と考え出す。しかし、まだ哲人を論破すること、跪かせることを諦めたわけでなかった…
・・・・・・・
さてさて、引用が長くなりましたが、自分なりに後で読んでも分かるようにと記載した次第です。
まず、第三夜を読んで疑問に思った「介入」と「援助」の違いに関するお話がありました。すべからく対人関係を「縦の関係」で捉えると、相手を従わせよう、操作しようとして「介入」してしまう。「横の関係」が構築できると素直な感謝、尊敬、喜びといった表現で、相手が自然に課題に立ち向かう勇気を持てるように「援助」できる、ということでした。それが「勇気づけ」なのだと。
本書に登場する青年同様、長年の競争社会で生きてきた富田にとって、なかなか身に染みついた「縦の関係」という捉え方をやめるのは困難に思えます。
それでも33年間の会社生活にピリオドを打ち、フリーランスとして活動を始めて約2年、この間にブログを通じた仲間達、社会人学校として通った「自分をつくる学校」卒業生のコミュニティ、SNSを通じて巡り会った「ソーシャルおじさんズ」コミュニティ、社会人版キムゼミ卒業生のコミュニティそれぞれのメンバーとの出会いを通じて、ずいぶん「横の関係」に馴染んできました。
20代から60代まで幅広い年代で、職業も趣味も様々な紳士淑女とのお付き合いを通じて「同じではないけれど対等」な関係を実感しています。そこに共通するのは、若かろうが尊敬し感謝できる仲間達、共に時間を過ごすことに喜びを感じる仲間達の存在です。
本書に書かれた「共同体感覚」をまさしく感じるところです。そして、これらコミュニティの中で「他者に貢献する」ことを心掛けてきたことによって、少しは自らの価値があるかな、と思えていることに感謝しています。
ということで、第四夜は富田の腹にストンと落ちた内容でした。(^_^)
・・・・・・・
さて、今日もすっかり長くなりました。次回は、いよいよ最終夜となる「第五夜 『いま、ここ』を真剣に生きる」について書く予定です。今度も、青年はなんとか哲人を論破しようと訪ねてきます。
ではまた!(^_^)
・・・・・・・・・・・・
(2014.2.25記)